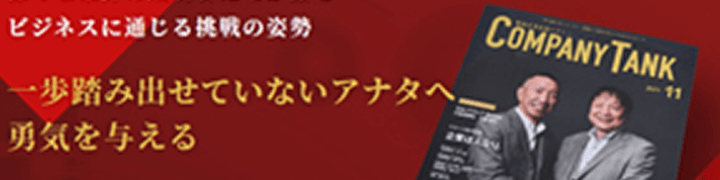巻頭企画天馬空を行く
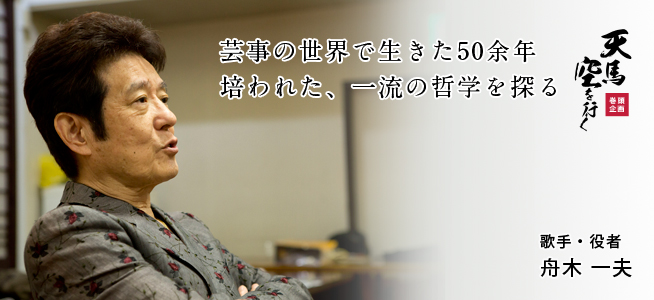
![]()
歌手・役者 舟木 一夫? Funaki Kazuo
1963年に「高校三年生」で華々しく歌手デビューを飾り、今なお現役で芸能界の一線をひた走る舟木一夫さん。現在では歌手としてだけでなく、娯楽時代劇でも座長として一座をまとめるなど、同世代の星であり続けている。波乱万丈な芸歴50余年の中で培われた芸事への哲学から、「顧客目線」へのヒントを探る。
1944年、愛知県に生まれる。1963年、18歳にて日本コロムビアより「高校三年生」でデビュー。発売1年で100万枚セールスの大ヒットを記録して第5回日本レコード大賞新人賞を受賞、一躍スター歌手となる。以降、歌手としてテレビやコンサートで活躍する傍ら、自身が座長を務める1ヶ月公演を毎年2回行い、好評を博している。2012年には芸能生活50周年を迎えた。
![]()
ツキが連鎖反応を生み、デビューへ
舟木一夫さんへのインタビューを行ったのは、2014年10〜11月に名古屋・中日劇場で行われた舞台「いろは長屋の用心棒」の稽古初日。一座の顔合わせ・配役発表を行った後、「読み合わせ」と言われる台本確認を実施する日だった。稽古を終えた舟木さんに「初日はいまだに緊張しますか」と質問をしてみると、「さすがに緊張することはもうないね。緊張を見せないのが、ベテランと新人の差。それがキャリアだよ」と、芸歴50余年の余裕と貫録を窺わせる。インタビューではまず、舟木さんの芸能生活における、スタート時のエピソードについて伺った。

舟木さんは愛知県一宮市出身。幼少期から流行歌手になりたいと思っていた舟木少年は、歌唱力向上や音楽知識の習得を目的とし、クラシック音楽の先生に師事していた。しかし、当時は歌謡曲とクラシック音楽の間には、今では考えられないほどの隔たりがあり、「クラシック歌手が歌謡曲を歌うことはタブー」とすら捉えられていた時代。そのため舟木少年は流行歌手への願望を隠し、クラシック音楽を学んでいたという。
そんな舟木少年に転機が訪れたのは高校2年の頃。当時の流行歌手・松島アキラのステージに足を運んだ時のことだった。
「僕の友達が、彼女と2人で松島アキラさんのショーに行こうとしていたのだけど、その彼女が部活で行けなくなったということで、僕に声をかけてくれたんだ。僕はショーが行われるジャズ喫茶という場所にはそれまで行ったことがなくて、どんなところなのかな、って感じでOKしたんです」。
2人の席は、前から2列目とステージに近い場所。そこでショーを堪能した最後、ステージ上の司会者から思いがけない呼びかけがあった。「どなたか、松島アキラのヒット曲“湖愁”を一緒に歌いませんか?」。
「そしたら、隣にいた友達が僕の手を掴んで挙げるわけですよ。前から2列目だから当然目立つわけで、司会の方が『じゃあ、そこの君』と僕を指名。そのままステージに上げられたものだから、そりゃ歌うしかないよね。ヒット曲だったから、歌う分には全く問題はなかったのだけど──」
無事に歌い終えてステージを降りた舟木少年に、1人の男性が声をかけてきた。それは、松島アキラのステージを取材しに来ていた記者。舟木少年の歌声に興味を抱き、連絡先を教えてほしいとのことだった。この時の彼の振る舞いや歌がホリプロダクション(現:ホリプロ)の創業者・堀威夫へと伝わり、「スター・舟木一夫」のロードマップが開かれていくこととなる。
そのエピソードを聞き、不思議に思ったことがあった。たとえ流行歌手への願望があったとはいえ、突然ステージに上げられて一曲をすんなりと歌いきることなど、よほどの度胸がないと難しいはず。そこで、「友達が舟木さんの手を掴んだ瞬間、実はチャンスだと思われたのでは?」という質問をぶつけてみた。
「いやいや、『何すんだお前?』って思ったよ(笑)。とはいえ僕も流行歌手を目指していたから、やはり人前で歌うことを前提に勉強しているわけですよ。そして、歌う機会が来たから歌った。それだけのことです。幸い知っている歌だったしね。
ただ、今になって思うと、物事がうまく転がったという巡り合わせの良さはすごく感じるよね。例えば僕の場合、松島アキラさんのショーに記者が来ていたからホリプロとの縁ができた。そして、たまたま友達が僕の腕を掴んで挙げたから歌を歌った。もっと言えば、友達の彼女の部活がなければ、僕はそこにはいないわけですよ。全てはたら・ればの話だけどね」
しかし、大半の人はそうした巡り合わせに気づくことはできない。
「僕も気づいていたわけじゃないよ。いずれは東京でデビューの糸口を探すつもりではいたけれど、それが向こうからやってきたというのは、やっぱりツイていたんだろうね。あてもない中でただ音楽の傍にいて、ツキが連鎖反応を起こしてすごいことになっていく。そんなこともあるのだなあ、というのが1961〜63年、デビュー前後の実感ですね」
巻頭企画 天馬空を行く
- ロンドン五輪ボクシングミドル級金メダリスト / 元WBA世界ミドル級スーパー王者 村田 諒太
- 元K-1ファイター 武蔵
- ヒップホップアーティスト / 実業家 AK-69
- サンドファクトリー / K-POP FACTORY CEO キム・ミンソク
- 元K-1スーパーバンタム級王者 WBO世界バンタム級王者 武居 由樹 × 元ボクシング世界三階級王者 大橋ジムトレーナー 八重樫 東
- 株式会社 サンミュージックプロダクション 代表取締役社長 岡 博之
- 元サッカー日本代表 / NHKサッカー解説者 福西 崇史
- スポーツクライミング選手 緒方 良行
- 元プロバレーボール選手 / 元プロビーチバレーボール選手 越川 優
- ガールズケイリン選手 / 自転車競技トラック日本代表 太田 りゆ