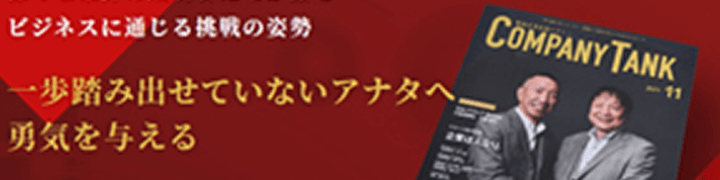巻頭企画天馬空を行く

元K-1ファイター
武蔵
 1972年10月17日生まれ。大阪府堺市出身。カンフー映画がきっかけで格闘技に興味を持ち、17歳の時に正道会館の道場生となる。その後、同会館の創設者である石井和義氏が立ち上げたK-1の盛り上がりに衝撃を受け、キックボクシングへ転向。1995年9月にK-1デビューを果たすと、翌1996年には「K-1 GRAND PRIX」で準決勝まで進むなど頭角を現す。相手の攻撃をかわしながらカウンターを当てるスタイル“武蔵流”を確立したことで、2003年、2004年の「K-1 WORLD GP」では2年連続の準優勝。「世界一のディフェンス力」とまで評価される。2009年に現役を退いて以降は、音楽と格闘技を融合させたイベント「MUSASHI ROCK FESTIVAL」を開催したり、俳優として映画・ドラマに出演するなどマルチに活躍。また最近はオリジナルの釣り具ブランドを立ち上げ、釣竿のプロデュースにも力を入れている。
1972年10月17日生まれ。大阪府堺市出身。カンフー映画がきっかけで格闘技に興味を持ち、17歳の時に正道会館の道場生となる。その後、同会館の創設者である石井和義氏が立ち上げたK-1の盛り上がりに衝撃を受け、キックボクシングへ転向。1995年9月にK-1デビューを果たすと、翌1996年には「K-1 GRAND PRIX」で準決勝まで進むなど頭角を現す。相手の攻撃をかわしながらカウンターを当てるスタイル“武蔵流”を確立したことで、2003年、2004年の「K-1 WORLD GP」では2年連続の準優勝。「世界一のディフェンス力」とまで評価される。2009年に現役を退いて以降は、音楽と格闘技を融合させたイベント「MUSASHI ROCK FESTIVAL」を開催したり、俳優として映画・ドラマに出演するなどマルチに活躍。また最近はオリジナルの釣り具ブランドを立ち上げ、釣竿のプロデュースにも力を入れている。
身長2m、体重100kg超――そんなスケールの選手が当たり前のように名を連ねるK-1ヘビー級の世界で、日本人としてただ1人、海外選手と互角に渡り合っていた男。それが、武蔵氏だ。デビュー直後の武者修行で格闘技を辞めたいと思うほどの挫折を味わいながらも、自分の可能性を信じて技術を磨き続け、たどり着いた高みから同氏が見たものは何だったのか。己を貫くこと、“武蔵流”の神髄に迫るインタビュー。
強さへの純粋な憧れから空手道へ
打撃系立ち技格闘技の最強を決めるというコンセプトのもと、1993年に設立された「K-1」。その最盛期である2000年代に、屈強な外国人選手がひしめくヘビー級で日本を背負って戦い続けていたのが武蔵氏だ。格闘家としての原点は空手。幼い頃から見ていたカンフー映画で活躍するジャッキー・チェンやブルース・リーへの憧れがきっかけだったという。
「幼少期の私はいわゆる“落ち着きがない子”で(笑)、興味が沸いたものは何でもやってみないと気が済まない性格でした。絵を描いたり、釣りをしたり···その中でも特に夢中になったのが、当時大流行していたカンフー映画だったんです。ジャッキー・チェンやブルース・リーの格闘シーンはもちろん、彼らが強くなるために作中で取り組んでいるトレーニングもぜんぶ真似をしましたし、悪を打ち倒す強者への純粋な憧れは、その頃から抱いていたように思います。空手を始めたのもその延長線で、17歳の時に格闘技好きの友人から『家の近くに空手道場があるから見学に行こう』と誘われて、自分が憧れる強さへ近付けるかもしれないという期待感から行くことにしました」
そうして武蔵氏が門戸を叩いたのが、正道会館だった。初めて練習を見学した時、体の大きい男たちが凄まじい迫力で打ち合う姿を目の当たりにした同氏は、恐怖より先に興奮を覚えたそうだ。
「普通、自分より大きな男の人が激しく殴り合っていたら、危ないとか怖いとか思いますよね。でも私は不思議とそうならず、むしろやられてみたい、打たれてみたいと思ったんです。これは私にマゾっ気があるからではなくて(笑)、この中で自分がどのくらい強くなれるのか実力を測ってみたい、彼らに挑んでみたいという気持ちが沸き起こったからでしょう。それに、ここに入れば間違いなく強くなれるという確信もありました」
実際、正道会館の道場生になった武蔵氏は、あっという間に空手道へのめり込んでいった。友人からの遊びの誘いも断り、時間さえあれば稽古に打ち込む日々。その時すでに、格闘家として人生を歩んでいく決意まで抱いていたと同氏は語る。
「正道会館には、佐竹雅昭さんという当時の格闘技界を席巻するほどのスター選手がいて、私は一道場生ながら、いつかはこの人を超えたい、それが自分の使命だとかなり早い段階から思っていました。もちろんそのためには乗り越えるべき課題が数多くありましたが、それさえも自分にとってはモチベーションになったんです。課題を全部クリアして、大会でも結果を出して、自分が入門したこの道場で一番強くなるんだ、と。そして、最終的には自分の道場を開いて師範になれればいいなと思い描いていましたね」
「初めてK-1の大会を観に行った時に、
自分が戦う場所はここだと確信しました」
しかし、そんな空手家としてのキャリアに思いを馳せていた武蔵氏の未来を大きく動かす出来事が起こる。それが、正道会館の創設者である石井和義氏による「K-1」設立だった。
「1994年に館長に呼ばれて初めてK-1の大会を観に行った時、超満員の横浜アリーナの地鳴りのような歓声に衝撃を受けたことを今でも鮮明に覚えています。普段一緒に練習している先輩たちが入場するたびに黄色い声援を受け、体を引っ張られるようにしながらリングへ向かっていて――道場生として、先輩がスターやアイドルのように応援されているのが嬉しかったですし、同時に自分もいつかはこうなりたい、自分が戦う場所はここなんだ!と強く思ったんです」
K-1転向、即デビュー
自分もあの夢舞台に立ちたい。その一心でK-1選手へと転向した武蔵氏は、1995年3月から本格的にK-1プロコースでの練習に参加し、そのわずか半年後の9月にデビューを果たすこととなる。初戦の相手は、当時“喧嘩屋・狂犬”の二つ名で大会でも実績を残していたパトリック・スミス。無謀とも思えるいきなりの強敵との対戦に、武蔵氏の心境はどのようなものだったのだろうか。
「最初にデビューを聞かされた時の感想として、さすがに嬉しさはまったくなかったですね(笑)。その時点ではまだスパーリングしかしたことがなく、実戦経験はまったくありませんでしたから。ただ、同じ時期に先輩の佐竹さんがケガで長期離脱されることになり、日本人選手がいなくなると盛り上がらないという事情もあって私に白羽の矢が立ったのでしょう。対戦相手のパトリック・スミス選手は、当時の“K-1四天王”の1人として君臨していたアンディ・フグ選手にも勝ったことがある実力者で、正直、日々のスパーリングでアンディさんに一方的にやられていた私が勝てるわけないだろうと思いました(笑)。その頃のK-1にはヘビー級しかなく、相手との体重差も20キロ以上···。絶望的な状況でしたが、最終的には『自分は今ふるいにかけられている。ざるの中に残れたら、次も試合に出られる』と言い聞かせ、覚悟を決めました」
迎えた対戦当日。自身の84戦のキャリアの中で最も怖かった試合と振り返る武蔵氏だが、いざ開始のゴングが鳴ると予想外にも冷静に立ち回り、真っ白だった頭も徐々にクリアになっていったという。
「対戦中のことはほとんど覚えていないのですが、後からVTRを見返すと、相手に対して一歩も退かず、それでいて冷静に立ち回っている自分がいたんです。そして、ローキックを蹴ったら相手がすごく嫌がって。『あれ?効いてる!?』そう思った瞬間、一気に意識がはっきりして、そこから後のことは覚えています。足が効いてガードが下がったところにハイキックがきれいに入って、相手が倒れたんです。私はそこで勝ったと思い、嬉しさのあまり飛び跳ねてしまいました。空手では一本勝ちですが、K-1はゴングが鳴るまで終わりではないので、だいぶ気が早かったですね···。結果的に、あのまま勝ちになって良かったです(笑)」
そんな初々しさを見せながらも、見事に強敵を倒し鮮烈なデビューを果たした武蔵氏。その後は勝ち負けを繰り返しながらK-1に順応していくことになるが、その過程で空手の素地が役に立ったかという問いには、意外な答えが返ってきた。
「空手とK-1は、打ったり蹴ったり、一見すると似ているところが多いと思われるのですが、それはラケットを持っているからテニスとバドミントンが似ていると言っているようなもので、実際には全然別物です。具体的には、顔を打たないルールで行う空手と、顔も打って良いルールで行うK-1とでは、必然的にK-1のほうが間合いが遠くなります。つまり、空手の感覚ではパンチが届かないし、蹴りも空手の外から回すやり方ではなく、腰を入れて蹴る必要があるんです。ざっと話してもこれだけ違いがある競技なので、私はK-1を極めていくうえで、空手で培ったものは一度捨てる決意をしました。空手の“貯金”だけで通用するほど甘い世界ではないだろう、と」
そうして武蔵氏は、K-1の基礎を1から身に付け、さらにK-1に通ずるボクシングやムエタイの技術も極めていった。するとある時、封印して意識の外にあったはずの空手の技が自然と出る瞬間があったのだという。
「あれは1999年のWAKO PROムエタイ世界ヘビー級タイトルマッチ、カークウッド・ウォーカー選手と対戦した時のことでした。4ヶ月前に5Rの判定で負けている相手で、その日も同じく5Rまでもつれたのですが、何とか勝ちたいという必死の思いからか、自然と空手時代から得意だった左のミドルキックが出て、それでKO勝ちすることができたんです。狙って、とか、空手の応用で、という感覚はまったくありませんでした。むしろそれまでにK-1の基礎を固め、間合いを測れるようになっていたからこそ、極限の場面で長年培ってきたものが出せたのだと思います。それがきっかけで、K-1の間合いでも空手の技を有効に使えるようになり、“左のミドルキック”が私の代名詞になっていったんです」

巻頭企画 天馬空を行く