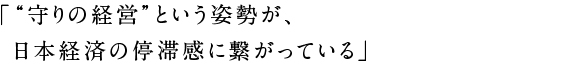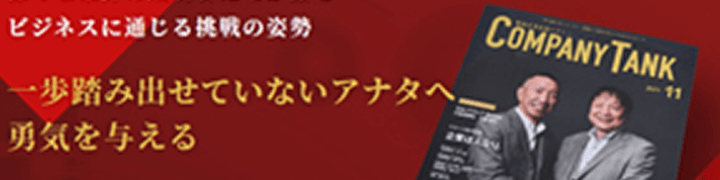巻頭企画天馬空を行く

![]()
田原 総一朗 Tahara Soichiro
フリージャーナリスト
1934年、滋賀県彦根市に生まれる。53年に滋賀県立彦根東高等学校を卒業後、作家を志して上京。日本交通公社(現JTB)で働きながら早稲田大学第二文学部日本文学科(夜学)に籍を置く。後に再入学した早稲田大学第一文学部史学科を60年に卒業後、岩波映画製作所を経てテレビ東京の開局と共に入社。77年にフリージャーナリストとしての道を歩み始め、以後あらゆるメディアを通じて社会の真実を伝えてきた。テレビ朝日系列の討論番組「朝まで生テレビ!」の司会者としてもお馴染み。
近江商人の末裔として生まれた軍国少年は、海軍に入ることが全てだと思っていた。しかし11歳のとき、終戦。それまでの価値観がひっくり返ったことで「世の中に絶対はない」と知る。その原体験が自身のジャーナリズムを醸成させ、日本を代表するジャーナリストとして存在感を示し続けている。そんな田原総一朗氏に、終戦直後から現在に至るまで見聞きし肌で感じてきた社会の真理を、忌憚なく語って頂いた。
![]()
経営者の思考の推移
 1977年にテレビ東京を退職して以降、フリーのジャーナリストとして政治・経済・文化などあらゆるジャンルの取材を精力的に手がけてきた田原総一朗氏。偏りがちな各メディアの報道に惑わされることなく、自らの足と目と耳で稼いだ情報は真に価値があると言える。そんな田原氏の目には、今の日本企業は総じて次のように映っているという。
1977年にテレビ東京を退職して以降、フリーのジャーナリストとして政治・経済・文化などあらゆるジャンルの取材を精力的に手がけてきた田原総一朗氏。偏りがちな各メディアの報道に惑わされることなく、自らの足と目と耳で稼いだ情報は真に価値があると言える。そんな田原氏の目には、今の日本企業は総じて次のように映っているという。
「『デフレの正体』を書いた地域エコノミスト、藻谷浩介さんの著書『里山資本主義』のなかに出てくるのだが、各企業が発表する新製品の約52%が2年で市場から消えるというのが、今の日本経済の実情です。一昔前までは5、6年のサイクルだったものが今は2年で見切られ、次々に新しい商品を投入しないと消費者に飽きられてしまう。ヒット商品と言えど、儲かる期間は約1年半と言われている。そうした新商品開発へのサイクルが短くなっていることが、今の企業経営の難しいところだと思う。
それにね、ライバル企業は国内だけでなく国外にも現れるようになった。振り返れば80年代頃までは、日本製品の質は抜群に良かった。“世界のソニー”と崇め賞されるほど、本当に群を抜いていた。つまり競争相手がいなかったわけだ。でも、ここ10数年のあいだに日本の真似をした韓国や中国企業が台頭し、日本と遜色のない品質の製品をプロデュースできるようになった。しかも安い。それで特に製造業は劣勢を強いられていますが、こういう時代だからこそ付加価値のある製品開発が求められている」。
商品開発サイクルの激化、海外企業も含めた競争の激化。これが今の日本企業が頭を悩ます部分であり、そのうえでプラスアルファの独自性をどこに見出すかが企業浮沈の鍵を握る時代でもある。それともう1つの懸念は“経営者の姿勢”にあると指摘する。
「戦後間もない頃は、ソニーの盛田昭夫さんやホンダの本田宗一郎さんといった名だたる創業者に代表されるように“マーケットにないものをいかにして創るか”という時代だった。いわゆるチャレンジの時代ですよ。当時は世の中にないものを開発し、それを啓蒙していくことも同時に求められた。
1950年頃にソニーが独自に開発したテープレコーダーを例に取ると、録音とはどういうものか、テープレコーダーで何ができるのかということを、ほとんどの人が知らない。だからソニーはまず、世の中の人々にその価値を理解してもらう必要があった。でも、市場への供給ルートが分からないわけです。そこで盛田さんは記録が必要な裁判所に目を付け、最高裁判所にそれを売り込みに行った。すると使い勝手の良さを知った全国の裁判所がテープレコーダーを購入するようになり、一般にも広まっていった。流通経路が完備された既存製品とは異なり、市場へ投入する販路の開拓から始める必要があったんです。だからもう、攻め続けるしかなかった。
ところが高度成長と共にチャレンジし続けた各企業は、経済成長の鈍化と共にチャレンジ精神を失っていった。規模が大きくなるがゆえリスクや失敗を恐れて無難な道を歩むようになり、 “攻めの経営”ではなく“守りの経営”がいつしか主流になっていったからです。しかし企業が成長を続けるにはチャレンジをし続けるしかない。つまり日本経済に停滞感が漂っているのは、“守りの経営”というのが一番の問題だと思っている」。
ニーズを制するものは市場を制す
国内企業の守りの姿勢が、かつてはトップクラスにあった国際競争力や国内総生産を引き下げていると田原氏は指摘する。しかしそのなかにあって、独自の事業展開により業績を伸ばしている企業も当然ある。1つの好例を教えてくれた。
「コマツブランドでお馴染みの建設機械・重機械のメーカー、『小松製作所』ってありますよね。実はこの会社は今の時代、すごく伸びている。コマツの姿勢は“顧客が欲しいもの・必要なものを、欲しいとき・必要なときに提供する”。それを実現するため同社がまず着手したのは、現状を把握することだった。10数年ほど前からほぼ全ての建設機械にGPS機能を搭載し、全世界のどこでどれだけの台数が稼働しているか、導入して何年経っているか、燃料がどれくらい残っているかというところまで把握できるようにしたのだ。
そうすることで小まめにメンテナンスができたり、建設機械が故障したときに先回りして対応できたり、得たデータを必要に応じて顧客企業や販売代理店に公開することが可能になった。一般的に建機は1台購入すると耐用年数を終えるまでに購入価格の約3倍のメンテナンスコストがかかるそうだが、こうしたコストを抑制することにも繋がっている。こうした付加価値がまさに、業績好調の原動力なんですね。
以前にコマツの相談役特別顧問、坂根さんはこう言っていた。『リストラは経営悪化してからするな、むしろ調子のいいときにやれ』。通常とは逆の発想ですよね。何故かと聞いたら『業績が落ちてからのリストラは単なるコストカットで、経営者の経営戦略がない。そんなことでうまくいくわけがないじゃないか』と。逆に考えると、コマツは新しいことに挑戦し続ける優れた経営戦略があったからこそ、伸びているとも言える」。
事実、コマツの幹部は10年間の豊富な経験を元に「他メーカーより3〜4年
は進んでいる」と自信をみせる。国内工場の効率化投資に今後3カ年で300?500億円を充てる方針を明らかにし、国内の工場を次々に建設。中国景気の減速などを機に国内拠点のコスト競争力を引き上げ、グローバルな構造改革のモデルを構築するのが狙いだ。「国内電気代の半減を早期に実現し、為替レートに左右されず国内生産を維持できる体制を築く」というコマツの姿勢は、まさに攻めの経営と言えるだろう。
「コマツが成功しているのは結局、今風に言えば“ビッグデータ”を有効活用したからなんですよね。それを冷静に見つめることで、消費者が求めているものが見えてくる。例えば今、店舗を構える書店では3ヶ月〜半年置いて売れない書籍は次々に返本されて、売り場にはもう並びません。でも、オンライン書店であれば陳列スペースに限りがないのでより多くの在庫を抱えることができる。結果、一年が過ぎてからベストセラーになるという、いわゆるロングテール現象が起こることがままあるんです。つまり、ユーザーが商品を購入する動機が変わっている。刻一刻と変化するそうしたニーズにいかにして対応していくかが、いわば業績を左右する時代だと思います。
時流に対応するという意味では、大手コンビニ・ローソンの例が分かりやすいかもしれない。これはローソンの新浪社長から直接聞いたのだが、かつてローソンはテレビCMをどんどん打っていた。それによって誰もがその存在を知るようになり、徐々にお客さんが足を運んでくれるようになった。そうなると次の段階で大事なのは、サービスの質や品揃えだ。だからテレビCMを止めて広告費を抑え、組織全体でサービスの拡充に努めた。結果、コンビニ業界で大きなシェアを獲得するに至っている」。
巻頭企画 天馬空を行く
- マルチタレント/ 歌手 中川 翔子
- ロンドン五輪ボクシングミドル級金メダリスト / 元WBA世界ミドル級スーパー王者 村田 諒太
- 元K-1ファイター 武蔵
- ヒップホップアーティスト / 実業家 AK-69
- サンドファクトリー / K-POP FACTORY CEO キム・ミンソク
- 元K-1スーパーバンタム級王者 WBO世界バンタム級王者 武居 由樹 × 元ボクシング世界三階級王者 大橋ジムトレーナー 八重樫 東
- 株式会社 サンミュージックプロダクション 代表取締役社長 岡 博之
- 元サッカー日本代表 / NHKサッカー解説者 福西 崇史
- スポーツクライミング選手 緒方 良行
- 元プロバレーボール選手 / 元プロビーチバレーボール選手 越川 優