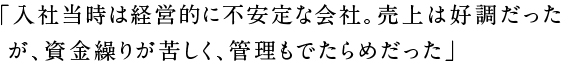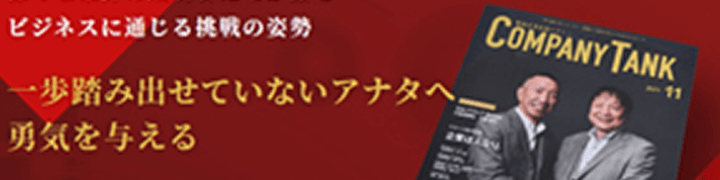巻頭企画天馬空を行く

![]()
堀江 康生 Horie Yasuo
株式会社 イエローハット
代表取締役社長
1952年京都市生まれ。京都工芸繊維大学繊維学部卒業後、繊維会社を経て1976年に(株)ローヤル(現:イエローハット)へ入社。名古屋や仙台の支店などで勤務したのち、1987年より本社へ。その後、常務取締役などを経て2008年10月より代表取締役社長に就任した。
敢えて挙げるまでもないが、周辺環境も厳しい。「若者のクルマ離れ」と言われて久しい現在、競合他社はもちろん、自動車メーカーやタイヤメーカーによる競合ショップの台頭、さらにネット通販やオークションと、業界地図は混沌としてきている。
会社も業界全体も厳しい状況であったにもかかわらず、堀江社長は就任するやいなや次期の黒字化を公言。そしてその言葉通り、会社の業績は急回復し、2期連続赤字からの黒字化を実現させた。この快挙は様々なメディアでも取り上げられたが、社長の活躍はそれだけに留まらない。積極的な出店攻勢にも手を緩めることなく、単純に数字を追いかけてみても常に右肩上がり成長を続けている。
この躍進の秘密はどこにあるのか─。それを含めて、堀江社長のこれまでの人生とその経営哲学から、混迷の時代を乗り切るヒントを探る。
![]()
インタビュー・文:青山 義明 写真:大木 真明
このままでは人生設計がまともにできない

京都市出身の堀江康生氏は、京都工芸繊維大学で繊維を学んだ後、繊維会社でニットの機械エンジニアとして社会人のスタートを切った。しかし、わずか2年弱でその会社を辞めている。このつまずきを「最初の勘違い」と、堀江氏は苦笑する。
「教授の推薦だからしっかりした会社だと思っていましてね。ところが、翌年冬のボーナスが遅配になったんです。12月にもらうはずが、1月の支払いになった。そのあたりで、『えぇ?』となったわけです。あくまでボーナスの話で、給料自体の遅配ではないのですが、自分がこれから働いていく中でキチッともらうものを然るべきタイミングでもらえない会社というのはどうかなあと。やる気も出てこないし、将来の人生設計ができないと思って・・・。その会社では非常にかわいがってもらいましたし、待遇もそれなりに良かったんですけど、数年経って後悔するより早いとこ辞めたほうがいいと、スパッと辞意を固めたんです」
社員が安心して働けなければ、良い会社とはいえない─この最初のつまずきから学んだ教訓は、のちのちの堀江氏のイエローハットにおける経営哲学に大いに影響することになる。
潔く辞めた堀江氏が次に入社したのが、(株)ローヤル。イエローハットの前身である。
「2度目の勘違い」で現在の会社に
(株)イエローハットは自動車関連用品の一般小売店をチェーン展開している会社、という認識が強いが、もともとは自動車用品の卸問屋である。(株)ローヤルが一般小売を始めたのは、堀江氏が入社する直前の1975年のことだったが、業務のウエイトとしては微々たるもの。商売の中心は圧倒的に「卸売業」であり、堀江氏もその世界に身を投じたのである。
給料がきちんとしている会社、ということで入社したのだが、堀江氏はこの入社を「2度目の勘違いだった」と語る。
「ボーナスは10ヶ月が実績、臨時ボーナスも毎年出るという話だったんです。それをうっかり信用しまして(笑)。臨時ボーナスは最初の頃に1回出ただけ。ボーナスも基本給ベースで少なかった」
建前と現実との違いは待遇面だけではなかった。「非常に経営が不安定で危ない会社だった」と当時を振り返る。
「表向きは業績が非常に良くて、増収増益の右肩上がりの会社だったのですが、資金繰りで苦労していたんです。現金回収でなく手形回収の卸問屋ですから、売上が伸びれば伸びるほど厳しくなります。他にも、買収した会社に簿外債務などの隠れた負債があったりで、当時の経営陣は非常に苦労されていました。
安定した会社と思って入ったのに、実は全然安定していない。その当時はフラフラの会社だった。もちろん、今は違いますよ(笑)」
ボーナスの遅配が原因で辞表を提出した前社同様、堀江氏の頭の中で辞意は何度もよぎったという。だが、2度目の見切りはなかった。
「それなりに不満や悩みごとはありましたが、会社に入ってからずっと忙しかった。あまりに忙しくて、辞めることを考える暇がなかった、というのが事実です。実は辞表を出したことも1回あるのですが、仕事、仕事で辞めるところまではいきませんでしたね」
忙しくてそれを考える間もなく、ということが主たる要因だろうが、それでも常に成長を続けていた会社に魅力を感じていたことも確かだろう。
名古屋支店での管理能力が認められ、仙台支店へ
「その当時は売上が右肩上がりでしたから、非常に活力があった。元気がありましたねぇ。商売として時代に合っていたんだと思います。利益も高くて、卸売の利益率は20%を軽く超えていました。
しかし管理がでたらめでして・・・営業マンが商品を適当に車に積んで売ってくるだけ。棚卸しをすると数が全く合わない。ともかく、管理がいいかげんな弱小問屋でしたよ(笑)」
その後、名古屋支店へ赴任。もちろん名古屋支店でも数が合わない、商品が消えてなくなっているという状態は変わらなかった。堀江氏は、忙しい業務の合間に、在庫管理の業務にも積極的に取り組んでいく。いろいろと在庫管理に改善を重ねる堀江氏に、あるとき支店長から声がかかった。
「仙台の在庫が合わないんだ。向こうへ行って在庫を管理してもらえないか」
当時の名古屋支店長は名古屋だけでなく、仙台の支店長も兼任していた。名古屋での管理能力を買われての大抜擢だった。
巻頭企画 天馬空を行く
- ロンドン五輪ボクシングミドル級金メダリスト / 元WBA世界ミドル級スーパー王者 村田 諒太
- 元K-1ファイター 武蔵
- ヒップホップアーティスト / 実業家 AK-69
- サンドファクトリー / K-POP FACTORY CEO キム・ミンソク
- 元K-1スーパーバンタム級王者 WBO世界バンタム級王者 武居 由樹 × 元ボクシング世界三階級王者 大橋ジムトレーナー 八重樫 東
- 株式会社 サンミュージックプロダクション 代表取締役社長 岡 博之
- 元サッカー日本代表 / NHKサッカー解説者 福西 崇史
- スポーツクライミング選手 緒方 良行
- 元プロバレーボール選手 / 元プロビーチバレーボール選手 越川 優
- ガールズケイリン選手 / 自転車競技トラック日本代表 太田 りゆ