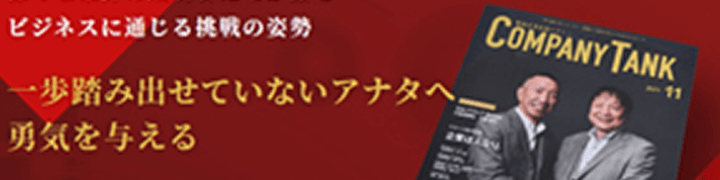巻頭企画天馬空を行く

![]()
伊藤 彰
日本サブウェイ株式会社
SUBWAY JAPAN,INC.
代表取締役社長
1958年神奈川県生まれ。明治大学商学部卒業後、1982年にサントリーへ入社。4年間、千葉エリアで酒類の営業を担当し、海外事業部へ異動する。スペインやメキシコで外食関連事業に関わるなど、十数年にわたりグローバルな飲食シーンで活躍。1998年、サントリーが筆頭株主を務める日本サブウェイ(株)へ出向し、同社のフランチャイズ展開について尽力する。2003年に代表取締役に就任。以降、数々のブランディング施策により企業イメージと業績を大きく変え、店舗数を飛躍的に増やし続けている。
![]()
アメリカ発の外食業態を日本に根付かせたブランディング
2011年、日本におけるサブウェイの出店数が300店舗を超えた。91年にアメリカのSUBWAY社とマスターフランチャイズ契約を結んで以来、20年間での成果である。チェーンビジネスという世界において、20年で320店舗は、決して驚くべき数字ではないかもしれない。しかし、同じ320もサブウェイの場合は毛色が異なる。「地に足がついた320店」とでも言うべきか。本部の完全なコントロール下において、数字やルールによってマニュアル化されたチェーン展開ではなく、各店舗のオーナー、そしてアルバイトスタッフにまでサブウェイの「理念」が浸透しているうえでの多店舗化なのだ。そのビジネス構造、集合的精神構造を作り上げた伊藤彰は語る。
「私が代表取締役に就任したのが2003年の10月。そのとき、日本では100店舗弱が出店していましたが、『これからどう展開していけばいいのだろうか?』と頭打ちの状態にあったのです。景気の影響ももちろんありましたが、日本ではサブウェイがなかなか浸透しきっていなかった。単純に考えれば、広告を出稿して認知を拡大し、売上を取り戻すという発想になりがちですからね」。
サブウェイが最初に取り組んだのは業態の変化だった。2004年からさまざまな業態にチャレンジしはじめる。
「サブウェイの主商品はコールドサンドイッチです。つまり、テイクアウトに向いている商品のためテイクアウト率が高い。そこに特化した商品をやってみることにしたりね。さらにはスターバックスさんのようなカフェの隆盛期でもあったため、充実したメニューを生かしてカフェに振ってみてはどうかとか。実にさまざまな紆余曲折がありましたね」。
しかし、どれも一過性のものにすぎなかった。テイクアウトの店は、最初はよく売れるものの、顧客の飽きが想像以上に早かった。サブウェイが得意とするイージーオーダーシステムのことを客側がよく理解できていなかったために、使いこなせないままになってしまい、結果的に客数のアップにはつながらなかった。
一方、カフェ業態の場合は、確かに顧客の目にはとまりやすくなったが、利便性が目的だった。さらにサンドイッチの世界的チェーンとしてのフードを提供できたとしても、絶対的なコーヒーのブランドを持っているわけではない。今度は客数こそ増えていけど、単価が下がり、結果的に売上が落ちてしまったのだ。そこで、最終的にはアメリカで培われてきた本来のやり方─つまり、カスタマイズするサンドイッチという原点に立ち返っていくのだ。
「サブウェイは知っている人からしたら、サンドイッチ屋なんですよね。だったら、そこにもうすでにブランドの芽がある。そこを確立していけばいいじゃないかと考え直しました。日本風に言うと、餅は餅屋、ってことだったわけです(笑)。ただし、店のサイズには少しアレンジを加えましたね」。
それまでサブウェイの店舗は30〜40坪が中心。しかし、フランチャイズ開始から統計を取ると、成功している店の多くが15〜20坪前後のスペースだった。
「そもそもサブウェイの調理に火は使いませんから設備投資資金が多くはかからない。しかもランニングコスト面でも、ほかの飲食業態に比べて負荷が軽い。そのうえで、15〜20坪であればインテリアへの資金も軽減できるので、いかにコンパクトな店舗スケールを実現していくかが大きなポイントとなりましたね」。
つまりオーナーとしては、1店舗に多額の資金をかけるのではなく、複数店舗に経営を分散化して、リスクマネジメントができる。これは他のフランチャイズチェーンにはない、サブウェイならではの大きな魅力だった。
そうしていくうちに、店舗数の拡大にともなってサブウェイの認知度も高まりを見せ始める。しかしながら、認知度の拡大がすなわちブランディングの成功とはつながらない。そこで、次は外向けのブランディングを行うために広告戦略を考えるようになるのだが─、
「拡大を始めたと言っても、まだ地域への定着率が決して芳しいとは言えない状態だった。広告を打ったところで、薄いリアクションしかないのは目に見えている。そこで、広告やPRを考える前に、日本における独自ブランドを構築しないと先がないと考えたのです」。
巻頭企画 天馬空を行く
- マルチタレント/ 歌手 中川 翔子
- ロンドン五輪ボクシングミドル級金メダリスト / 元WBA世界ミドル級スーパー王者 村田 諒太
- 元K-1ファイター 武蔵
- ヒップホップアーティスト / 実業家 AK-69
- サンドファクトリー / K-POP FACTORY CEO キム・ミンソク
- 元K-1スーパーバンタム級王者 WBO世界バンタム級王者 武居 由樹 × 元ボクシング世界三階級王者 大橋ジムトレーナー 八重樫 東
- 株式会社 サンミュージックプロダクション 代表取締役社長 岡 博之
- 元サッカー日本代表 / NHKサッカー解説者 福西 崇史
- スポーツクライミング選手 緒方 良行
- 元プロバレーボール選手 / 元プロビーチバレーボール選手 越川 優