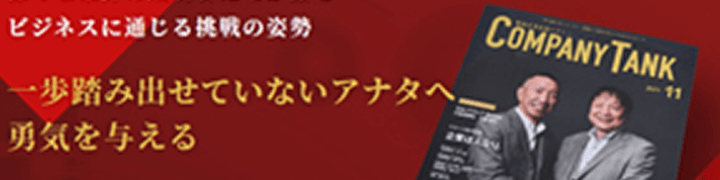巻頭企画天馬空を行く
「自分で指名して入団したからこそ、すぐに
結果を出すという覚悟を持っていました」
念願の中日ドラゴンズ入団
社会人野球での濃密な3年間を過ごし、福留氏は1998年に逆指名制度を使って念願の中日ドラゴンズ入団を果たした。“相思相愛”での入団だったが、当時の心境を改めて訊ねてみると、意外な答えが返ってきた。
「自分で指名して入団させていただいたからこそ、当初は逆に不安な気持ちがありました。本当に大丈夫か、しっかり活躍できるか、と。高卒とは違い、社会人上がりだからこそ、入団してすぐに結果を出さなければならないと自覚していましたし、数年で良い成績が残せなければ辞めることになるという覚悟を持って入団しましたね」
チームからの期待も大きく、新人ながら開幕からスタメン起用をされた福留氏は、その年のオールスターゲームにも選出される活躍を見せ、シーズン成績も打率.284、本塁打16本と上々の成績でチームのリーグ優勝に貢献した。しかし、そのことについて同氏は自分の力ではなかった、と謙虚に振り返る。
「皆さんは私が1年目から活躍したと評価してくださるのですが、あれは私自身の活躍というより、1年間使い続けてくださった当時の星野仙一監督の“我慢”のおかげだったと思っています。開幕から『ショートは孝介でいくぞ』と伝えられて、その後はどれだけミスをしたり不振に陥ったりしても、チャンスを与え続けてくださったんです。だからこそ、私も必死になれたのかもしれません。当時は無我夢中でしたが、野球をしている時間が好きだったので、苦しいという感覚はまったくなかったですね」
ところが、2年目・3年目はケガにも悩まされて思うような成績が残せず、ポジションもショートから外野へコンバートすることになった福留氏。“4年目も悪ければクビだろう”という考えも頭をよぎる中、その年に入団してきた打撃コーチとの出会いが大きな転機となる。その人物こそ、かつての7球団競合のドラフト当時に近鉄バファローズの監督をしていた、佐々木恭介氏だった。
「ある日、佐々木さんが私のところにやって来て、『1年間、俺の言うことだけを信じてやってみろ。そうしたら“億”稼げる選手にしてやる』とおっしゃったんです。よく考えるとものすごい話ですが(笑)、その時は自分でもやり方を変えたいと思っていたタイミングだったので、不思議とその言葉がすんなり入ってきて、二つ返事で『わかりました、すべて言う通りにやります』と言いました。それからは、タイミングの取り方や構えている手の位置など、バットを振る動作以外はすべてと言ってよいくらい、何もかもを変えていって――佐々木さんとは『お前があの時に近鉄に来ていればもっと早く教えられたのに』『いやいやあの時にプロに行っても失敗していましたよ』と言い合いながらも(笑)、本当に信じて1年間やり続けたんです。それが最終的に首位打者という結果につながったので、心から感謝していますね」
改造と不調、その先に生まれた伝説
2002年は首位打者に加えてベストナイン、ゴールデングラブ賞のタイトルも獲得し、福留氏にとってはまさに飛躍の年となった。それ以降も2003年と2005年に最高出塁率を獲得するなど、チーム内はもちろん球界をも代表する打者へと成長を遂げたが、同氏は現状に満足することなく、さらなる安定性を求めて2005年のオフに打撃フォームの改造に着手する。しかし、新フォームが固まり切る前にやってきたのが、2006年3月に開催された第1回WBCだった。
「日本代表に選ばれたことは嬉しかったですが、当時はフォーム改造の真っ最中で、何も固まっていない状態だったので、参加してもチームのためにならないだろうと、実は1度目のオファーは断ったんです。でも、その後に監督の王貞治さんから『どうしても出てほしい』と2度目のお声掛けをいただいて――王さんから2度誘われて断る勇気はなかったので(笑)、事情はお伝えしたうえで参加することを決意しました」
そうして始まったWBC本戦。福留氏の予感通り、準決勝に至るまでのリーグ戦ではなかなか結果が出ず、苦しい時間を過ごすことになった。
「気持ち的には、どちらかというと諦めというか、“ほらな”という感じでした。実戦の中で、もう少しこうかな、とか、こうしてみよう、と思っても、大会中は試合の連続なので練習の時間もなかなか取れなくて。それでも、その場で自分がやれることをやっていくしかないと考えていましたし、ちゃんと前を向くことはできていたかなと思います」
日本は準決勝進出を懸けた2次ラウンドで1勝2敗となり、敗退するかと思われたが、最終的に日本、アメリカ、メキシコの3チームが同戦績で並び、得失点の差によって辛くも準決勝へ進出。起死回生の出来事だったものの、福留氏は複雑な心境を抱いていた。
「自力での進出ではなかったですし、頭の中は少し日本に帰ってからのことに切り替わりかけていたんです。もちろん、結果を知った時は“やってやるぞ”という気持ちが芽生えましたが、それまでの成績から考えて次も駄目かもしれないという不安もあって···。すると、翌日の練習時に王監督から『準決勝はスタメンから外すよ。でも、必ずいいところで代打に行ってもらうから』と伝えられました。その瞬間は、ここで外れるのかという悔しさが3割、残りの7割は正直、良かったという安堵があったかもしれません」
そう心の内を赤裸々に語ってくれた福留氏。しかし、迎えた準決勝の韓国戦、7回表。不意に訪れたそのタイミングでは、それまでとはまったく異なる心境を抱いて打席に入ることになったという。
「お互い点が入らずに7回になって、先頭の松中信彦さんが2ベースヒットを打ったところで、“あ、代打が来るな”と直感的に思ったんです。その後にバントの失敗があって、そこで私は誰に呼ばれるでもなくベンチの階段まで出て行っていて。すると監督からも代打の指示が出たので、同じタイミングだったんだなと感じました。打席に立つと、今まで調子が悪かったこととか、代打だから初球から行くこととか、そういったごちゃごちゃしたことが不思議なくらい頭から消えて、本当の意味で自然体になれたんです。とても冷静で、時間もゆっくり流れていましたね。最初の2球を見送ったところで、次のボールを打てると感じ、振り抜きました」
結果はライトへの2ランホームラン。それが決勝点となり、日本は見事に勝利を収めた。勢いづいた福留氏は決勝戦のキューバ戦でも試合を決定づけるタイムリーヒットを放ち、優勝に大きく貢献した。その2打席の意味を、同氏はしみじみと振り返ってくれた。
「あの準決勝と決勝でホームラン、タイムリーと打てていなかったら、その後のキャリアでもずっと引きずっていたかもしれません。土壇場で結果を出せたからこそ、気持ちの切り替えをうまくすることができましたし、そのシーズンでも最終的に2度目の首位打者を取ることができたのだと思います」

巻頭企画 天馬空を行く