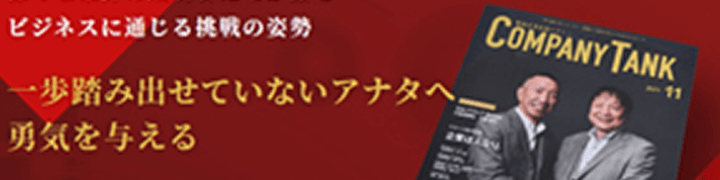コラム

日本人には鬼門とされるミドル級の道を切り開いた元ボクシング世界チャンピオン・村田諒太氏と、不動産業界に新たな視点を提示し日本の未来を変革する日本リアライズ(株)の大橋社長。10年以上の時間をかけて信頼関係を築いた2人は、互いに学び続けることをやめず、自らの哲学を常に洗練させ目標を実現してきた。今回は努力する方向の見定め方や原初体験の重要性など、2人だからこそ可能な、日々前進するためのメッセージを語ってもらった。
大橋 孝行
 大学卒業後、東京リコー(株)に入社。トップセールスマンとして活躍した後、30 歳で不動産業界に転身し、2009 年に日本リアライズ(株)を創業した。以来、ライフプランの提案を通じた住宅販売により着実に業績を伸ばす。2018年頃からは「ライフメイクプランナー」として、人生100年時代における理想の人生設計に積極的に貢献。2022年11月に(一社)人生診断協会を設立し、今までにない新たなマイホーム販売の形として新規事業「ライフメイクパートナーズ」を推し進め、その加盟店を増やすべく尽力している。
大学卒業後、東京リコー(株)に入社。トップセールスマンとして活躍した後、30 歳で不動産業界に転身し、2009 年に日本リアライズ(株)を創業した。以来、ライフプランの提案を通じた住宅販売により着実に業績を伸ばす。2018年頃からは「ライフメイクプランナー」として、人生100年時代における理想の人生設計に積極的に貢献。2022年11月に(一社)人生診断協会を設立し、今までにない新たなマイホーム販売の形として新規事業「ライフメイクパートナーズ」を推し進め、その加盟店を増やすべく尽力している。
ロンドン五輪ボクシングミドル級金メダリスト
元WBA世界ミドル級スーパー王者
 村田 諒太
村田 諒太
中学時代よりボクシングを始め、南京都高等学校(現:京都廣学館高等学校)では高校5冠を達成。2004年に東洋大学へ進学後、一度現役を退くも、2009年に現役復帰して以降、2011年世界アマチュアボクシング選手権準優勝、2012年ロンドン五輪ミドル級金メダル獲得と躍進を遂げる。2013年にプロに転向し、2017年に2度目の世界挑戦でWBA世界ミドル級チャンピオンに。2018年の防衛戦に敗れ王座から陥落したものの、2019年のリマッチにて再び返り咲く。2022年4月、日本人初の2団体王座統一戦を行い、2023年に現役を引退した。
10年以上信頼関係を積み重ねてきた2人
――まずはお二人の出会いやお互いの印象について教えてください。
 村田 もう10年以上のお付き合いになりますね。現役だった2016年から2018年の頃はよく食事にも連れて行っていただきました。何より人を嫌な気持ちにさせないお人柄で、大橋社長とお酒を飲む時間はとても楽しいんです。
村田 もう10年以上のお付き合いになりますね。現役だった2016年から2018年の頃はよく食事にも連れて行っていただきました。何より人を嫌な気持ちにさせないお人柄で、大橋社長とお酒を飲む時間はとても楽しいんです。
大橋 私からしたら村田さんはスーパースターのような存在ですから、逆によく付き合ってくれていたなという気持ちです。村田さんは哲学的な話もできる人なので、いろいろ言い合いながら食事を共にするのが、私も楽しいんですよ。だからこそ、最初から話が合って仲良くなれたのかなと思っています。
村田 大橋社長は出会った頃よりも貫禄があると言いますか、豊富な経験を積まれて言葉により一層深みが増してきたように感じます。言葉の端々から、さまざまな経験をされてきた方というのがよくわかるほどです。人付き合いも多いですよね。
大橋 ありがとうございます。村田さんは古典も好きな読書家で有名ですが、私の核にあるのは実は「少年ジャンプ」なんです(笑)。昔から友情・努力・勝利のキーワードが好きで、そうした思いを大切にできる主役になりたいと思っていたので、人をだますような姑息なことができないんです。だから、言葉を交わすことで信頼していただけるのかなと自分では思いますね。
――お話から、お二人の築いてこられた信頼関係が伝わってきます。大橋社長は以前ボクシングをやっておられましたし、日本リアライズ(株)さんは現在もボクサーのサポートをされています。そんな大橋社長の目から見た村田さんはどのようなボクサーだったでしょうか?
大橋 ストレートに言うと、とても規格外の選手でした。竹原慎二選手が日本人で初めてミドル級のチャンピオンになって以来、その後、誰もその座に座ることができなかった厳しい領域で金メダルを獲得し、プロになってからも世界チャンピオンに輝いたというのは、とてつもない偉業です。今後、日本の中でこのような選手はそうそう生まれてこないでしょう。
努力の目的を明確化し自己超越を図る
――村田さんには『折れない自分をつくる 闘う心』というタイトルのご著書があります。仕事で闘い続けるためのメンタル面の重要性について、村田さんのご意見をお聞かせください。
村田 スポーツ選手のメンタルが何で強いのかというと、自分のやりたいことを存分にできているからだと思っています。「このスポーツをやりたい」とほとんどの人間が自分の意志で決めて練習に励み、偶然その分野で才能があったからこそ、アスリートとして活躍できていますよね。好きなことや得意なことだからこそ耐えられているので、アスリートと一般的な会社勤めの方とは、根本的にメンタルという言葉の意味合いが少し異なっているように感じます。そういう意味では、自分のやりたいことに挑戦している起業家の方はボクサーと同じ方向性のメンタルを備えているのかもしれないですね。
――「苦しい・つらい」という気持ちが、「好き」という気持ちを上回ることはないのでしょうか?
村田 責任が大きくなるほどあるのではないでしょうか。私の場合は、オリンピックを目指すと言っていた頃は単純にボクシングが好きという気持ちだけで練習が続けられていましたが、世界選手権やロンドン五輪に出場して成績を残したことで、「日本人ボクサーによる48年ぶりの金メダルだ」と世間から評価していただき、ボクシングが自分の中で義務となり、大きな責任になりました。好きなことが義務に変わった時、人間は大きな負担を背負うと思うんです。
大橋 まさにその通りだと、私も思います。私も自分でがむしゃらに営業をしていた頃や会社を設立した当初は皆から評価をいただいて、勢いづいていましたが、徐々に会社が大きくなってからは、その責任の重さを苦しく感じたこともありました。そういう時にメンタルを強くするには、目的意識を持って、その実現のために努力することが重要だと考えています。自分の中で確固たる目的ができれば、後はそれを遂行するためにひたすら努力を続けるだけなので、どんな危機的状況に陥っても耐えられるんです。
――大橋社長はかねて「努力するためにはまず『目的』が必要」だと言っておられます。村田さんもある記事で「目標ではなく、『目的』が人生を豊かにする」と語っておられます。お二人がそれぞれ、仕事においてどのように目的設定をされているのか教えてください。
大橋 私の一番の目的は、マイホームを販売することでお客様の幸せをつくり、それによって子どもたちが豊かになる明るい未来を築くことです。だからこそ、当社ではお客様を第一に考えた、一番良いものを取り扱っているという自負があります。
村田 私がプロに転向した当初、「チーム村田諒太」を組んで世界チャンピオンをつくろうというプロジェクトが立ち上がりました。その際に、とある方から「君たちの目的は何?」と聞かれて、「世界チャンピオンになることです」と答えたんです。するとその方は、「それは目的ではなく、目標だ。目的というのは、より崇高で大きなことを指す」と言われました。私にはその際のやり取りがとても印象に残っていて、今でも改めて自分の目的を問い直さないといけないと感じています。その過程では、社会問題について考えることもあるんです。現在、日本では約7万人近くの自殺者が出ていますよね。公表されていないケースも含めると、約10万人はいるのではないでしょうか。それに、10代の若者の死亡理由で最も多いのも、自殺なんです。だからこそ、目的というと少し方向性が違うかもしれませんが、私は自殺者のいない社会をつくりたいと考えています。
大橋 私は、自殺をしてしまう根本的な要因は、自己肯定感が低いことだと思っています。そして、なぜ日本で若者の自殺者が多いのかというと、3歳までの育児の仕方にあると考えているんです。日本では、子どもが泣いている時に、抱き癖がつくと困るから抱っこをしないという風潮が根付いていますよね。しかし、3歳までの間に親から抱っこをしてもらい、自分を認めてもらう経験が少ない方は、自己肯定感が育まれません。そのことが、近年の若者の自殺者が増えている要因に直結するのではないかと思うんです。子どもの育児にとって最適な環境づくりをマイホームで実現させ、子どもが頑張った時にきちんと抱っこをしてあげられる余裕をつくる。「最高の抱っこ」を増やすということが、私が努力する一番の目的なんですよ。
――「闘う哲学者」の異名を持つ村田さんがお好きだというドイツの哲学者ニーチェは、「生きている間に、できるかぎり最も良い所へ昇りつめよう」とする努力を「力への意志」と呼び、人間にとって非常に重要なことであると論じました。大橋社長もニーチェのように「覚悟を持って努力する」ことの重要性を説いておられます。村田さんから「努力」することの意義についてお話しいただければと思います。
村田 努力がどういう方向に向かっているのか、よく考えることが大切だと思います。例えば、他者との比較をしてしまうと、そこから永遠に努力しても満たされることはないでしょう。あくまでニーチェが「努力」として説いているのは「自己超越」です。「自己超越」というのはつまり、常に自分の内側に幸福を見つけ出し、自分を変革していくこと。資本主義である現代においては、さまざまな領域においてプロパガンダのように「自己超越」という言葉が掲げられ、他者と競い合わせるために努力することを強いています。努力する方向性は自分の内側に存在するということを、忘れてはいけないですね。
大橋 村田さんの言う通りだと思います。私もマイホームを販売する中で売り上げが大きくなるにつれ、会社が傾いていった時期がありました。しかしそのタイミングで、子どもたちの幸せにつながる新しい事業をつくりたいと考え始めたんです。以来、毎日、自分を超えていく作業と向き合ってきました。
子どもの自己肯定感を高め幸福な社会を
――大橋社長は企業が社員に、マイホームと住宅ローンの知識の提供や、病気や災害のリスクから守るために必要な教育を行う『リアライズクラブ』という「新時代の福利厚生サービス」を通して、「問題を抱える世帯」「生活に困窮する家庭」を減らすことを提唱されています。
 大橋 ええ。これからの子どもたちが多種多様な目標を思い描き、自由に道を切り開いていくためには、自己肯定感を育むことが大切です。そして、そうした自己肯定感を育むためには、前述したように3歳までの育児の中で、子どもが頑張った時にきちんと抱っこしてあげられるような環境づくりと親御さんの余裕が必要です。しかし、親御さんにお金と時間と心の余裕をつくるための施策や教育というのは日本にはありませんし、親や先輩が教えてくれることもありません。だからこそ、当社の『リアライズクラブ』によって、導入した企業様から従業員の方へ知識が届けられたらと考えているんです。
大橋 ええ。これからの子どもたちが多種多様な目標を思い描き、自由に道を切り開いていくためには、自己肯定感を育むことが大切です。そして、そうした自己肯定感を育むためには、前述したように3歳までの育児の中で、子どもが頑張った時にきちんと抱っこしてあげられるような環境づくりと親御さんの余裕が必要です。しかし、親御さんにお金と時間と心の余裕をつくるための施策や教育というのは日本にはありませんし、親や先輩が教えてくれることもありません。だからこそ、当社の『リアライズクラブ』によって、導入した企業様から従業員の方へ知識が届けられたらと考えているんです。
――日本の未来を担う素晴らしいサービスだと思います。村田さんは大橋社長のこの試みをどのように思われますか?
村田 私はすべてのことにプラス面とマイナス面があると思うタイプなので、事業の詳細を完全に把握していない以上、大きな声で称賛も批難もすることなく、中立な立場でいるべきだと思っています。しかし、その事業の根本にあるのは「人の幸せって何だろう」という疑問ですよね。何を持って幸せとするのかは、人によって大きく異なります。例えば家族がいる安定した生活がしたいという方にとっては、こうした大橋社長の取り組みは最高の幸せを提供すると感じます。
――村田さんはあるインタビューで「教育は大人が子どもに与えることができる『ギフト』であり、ただ言葉を与えるだけではなくて、自分の経験を伝えることで子どもたちの持っている可能性を引き出すことが大切」だと語っておられました。また、先ほどのお話にもあった通り、大橋社長は「低迷する日本を救うには子どもの自己肯定感を高めることが必要であり、また子どもたちの幸せのためには親への教育が重要」と力説されています。お二人の教育観はとても興味深いのですが、村田さんは「親への教育が重要」という大橋社長の持論についてどう思われますか?
村田 自分が親になって痛感しましたが、親が子どもに教えるなんてとんでもない話だと思います。親も、常に学んでいるんです。私も子どもから学んでばかりで、自分が心から良いと思っていたことがただの押しつけだった、ということも多くあります。大人になると何でも知っているような錯覚が芽生えてしまいがちですが、当然われわれ大人も学んでいかなければならないですし、親への教育というのは絶対的に大切だと感じますね。
大橋 やはり、大人になると教わる環境がないですよね。私も自分が親の立場になり、親としてできていなかった部分が多々あります。その時、「どうしたらこれから親になっていく世代の人たちが、親として真っ当な対応ができるようになるのか」を考えて、どこかでその方法を教える必要性があると感じました。そこで『リアライズクラブ』を提供し、企業から従業員の方へ、安心して暮らせる住環境を整えるための知識を伝える仕組みを整えようと思い至ったんです。
――先述した『リアライズクラブ』は、会社に勤める社員の方々の「真の幸せを追求する」試みだと伺っています。少し大きな質問になって恐縮ですが、価値観が多様化している現代社会において、お二人が考える「真の幸せ」とは何でしょうか?
大橋 家族との平和な時間を過ごしたり、目標に向かって挑戦をしたりなど、幸せは人それぞれに正解があるものです。ですから、一人ひとりが自由に自身の思う幸せを追求していければ良いと思います。しかし、例えば自分の子どもと遊園地に行けば楽しい思い出がつくれますが、極端な話、帰宅した後に地震の影響で家が壊れて死んでしまったら、元も子もないですよね。また、賃貸のキッチン設備が不十分なせいで自炊が減り、健康を害したとしても、そうした状況の中では幸福を追い求める意味がありません。幸せを追求するためには、その土台となる家計と住環境の最適化が必要です。安心して暮らせる十分な環境を整えたうえで、自分のやりたいことに挑戦することが真の幸せだと思っていますし、それを実現するためにも、『リアライズクラブ』という福利厚生を提供しているんですよ。
村田 確かに幸福の形は人それぞれですから、何より自分の内側に向かって「何が幸せなのか」を考えられる瞬間があることが大事だと思いますね。また、人とのつながりにおける幸福も非常に重要だと感じます。もし大きな社会的成功を遂げたとしても、それを祝ってくれる他者がいなければ、それは幸福とは言い難いですよね。私も、先日中学校の同窓会がありまして、久々にいろいろな人と会えてとても楽しかったのを覚えています。大橋社長の掲げる「最高の抱っこ」も然りですが、いかに安心して人とつながれるかが、幸福の要になると思います。
――最後にお二人が、それぞれお互いの今後に対して期待することがあれば、ぜひお聞かせください。
大橋 村田さんとはかねがね、何らかの形でタッグを組み、一緒に何か挑戦していきたいと考えていました。私は将来的に、各分野のトップと組みたいと思っているのですが、ボクシングの領域で言えば、それはまさに村田さんなんです。具体的な内容は決まっていませんが、「抱っこの機会を増やす」という理念に通じるような挑戦を共に行い、今後の人生を共有しあえたら嬉しいですね。
村田 子どもにとっての抱っこのように、人の原初体験というのはとても大切です。「抱っこを増やす」ということは、「何かあったら甘えて大丈夫なんだよ」「君は愛されているんだよ」というシグナルになると思うんです。そうしたセーフティネットをつくり出す大橋社長の取り組みは、本当に今の社会だからこそ必要です。今後も、そうしたセーフティゾーンを増やし、子どもたちの幸せを増やせる活動を共にしていけたら幸いです。
取材:徳永 隆宏
文 / 構成:木村 祐亮
撮影:竹内 洋平