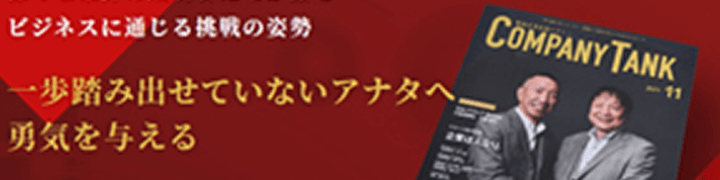コラム
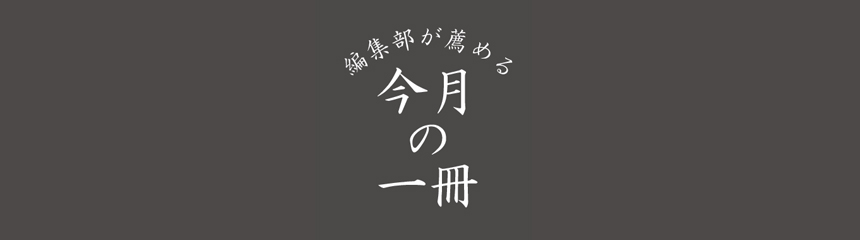
 自身の“あたりまえ”を疑え!
自身の“あたりまえ”を疑え!
社長の常識が生産性を下げている?
思い込みを捨て去り、組織の力を引き出そう!
帝国データバンクの調査によると、多くの企業が人手不足を感じており、特に中小企業は賃上げが難しく人材確保が困難な状況です。こうした中で中小企業が成長するには、今いる人材の力を最大限に引き出し、生産性を高めることが不可欠です。
本書の著者は、多くの経営者が勘や経験に基づく「勘違いマネジメント」を行っており、それが生産性向上の妨げになっていると指摘します。例えば、従業員を育てるつもりで過度な裁量を与える、社歴が長いという理由だけで管理職に昇進させる、中間管理職を飛び越えて直接指示を出すなど、良かれと思っての行動が、かえって組織の不調和を招いているというのです。
本書では、そうした勘違いマネジメントを「組織内コミュニケーション」「社員育成」「人材配置」の3つに分類し、その解決策として著者が自社で実践してきた取り組みや経営コンサルタントとして伝えてきた知見を紹介しています。中小企業経営者が自社のマネジメントを見直し、人材難の時代に競争力を高める助けとなる一冊です。
《著者Q&A》
■この本のポイント・読みどころを教えてください
マネジメントに絞った内容ではありますが、会社内で日常的に行われてしまいがちなマネジメントのミス、起こりうるエラーとその改善策を多く書いていますので、共感いただける内容も多いと思っております。
■この本を特にどんな人に読んでもらいたいですか?
経営者をはじめ、部下や教育指導に関わるすべての人とこれから管理職を目指す方々を対象としております。
■大石社長が考える「風通しの良い職場環境」とはどのようなものでしょうか?
暗黙のルールがなく、社内の規制、会社が求める結果が末端の社員にまで伝わっている環境だと思います。
■多様なバックグラウンドを持つ働き手がいる中で、“公平な評価”を実現するためにはどのような仕組みや工夫が必要でしょうか?
明確な評価基準の設定に尽きると思います。求める量、質、時間を明確に設定すること、明確な基準で「できた」「できなかった」の判断までを行えることだと考えています。
■経営者としてお仕事をするうえで特に大切にされていることは何ですか?
自分を含めた組織内に属する者全員に対する役割設定、その徹底です。
■本誌の読者に向けてメッセージをお願いします。
長年経営者の立場で組織運営をしてきた中で、特に従業員との向き合い方は常に課題でした。私の経験から学んだマネジメントの活用術でもありますので、ぜひ参考までに軽い気持ちで読んでいただき、1つでも組織の問題解決になることがあれば嬉しく思います。
| 大石 和延(おおいし かずのぶ) 1978年東京生まれ。1998年にアルバイト先の関連会社社長の勧めで起業。初めは軽トラック1台で中堅運送会社の下請け業務からスタートし、3年後に法人を設立。2003年に株式会社へ組織変更。2004年に倉庫・物流・製造業に特化した人材サービス事業を開始、2007年ビーエスロジスティクス(株)設立、3PL事業を開始。2013年に(株)BS、ビーエスロジスティクス(株)の持ち株会社として(株)BSホールディングスを設立。2014年に東京神田にて通関会社を設立、2016年にトランクルーム宅配サービスの(株)ものくるを設立、2020年に大阪市の関連会社を買収し現在はビーエストレードアンドフォワーディング(株)と合併させ同社大阪支社に、2021年に冷凍冷蔵倉庫専門の物流事業のビーエスプラスチルド(株)を設立して物流サポートの対応領域を拡大しながら現在に至る。2018年に(株)OEC法人サポートを設立し、現在は組織運営の講師としてさまざまな業種の組織構築をサポートしている。 発行:幻冬舎メディアコンサルティング URL https://www.gentosha-mc.com/ 発売:幻冬舎 URL https://www.gentosha.co.jp/ |
<< 編集部が薦める今月の一冊No18|編集部が薦める今月の一冊No20 >>